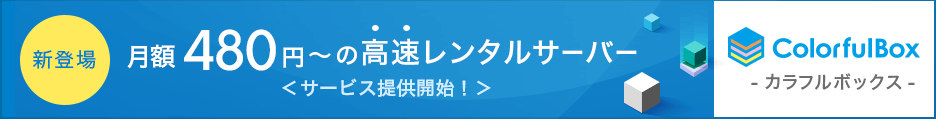
3 闇の樹海から距離を取った、ロストン聖教国の森の中。一時撤退した連合軍が野営地として選んだのは、二本の河川が交差して作られた中州であった。 行軍に不可欠な水を豊富に得ることが出来る中州は、増水の心配さえなければ見渡しの良さもあって、天然の砦のような防衛力を発揮する。火責めを恐れる必要も無く、優れた射手とフレリアの天馬部隊を擁する連合軍にとっては、これ以上無い有利な地形である。 そうしたゼトの判断を指揮官代理であるエイリークが採用し、一向は仮設した拠点で戦闘の疲れを癒していた。すでに空には新円にわずかに足らない月が昇り、完全に夜の帳が下りた時間帯だ。 エフラムが目を醒ましたのは、彼専用に仕立てられた指揮官用の天幕の中でであった。 「つ……っ」 「兄上! お気づきになりましたか」 肩の引きつるような痛みに顔をしかめ、エフラムが上半身を起こすと、まず一番最初に飛び込んできたのは心配げな双子の妹の顔であった。四、五人が入ればいっぱいになってしまう天幕の下、カンテラのわずかな灯りに照らされて一人ずつの男女が彼のそばに控えていた。 女はエイリーク。男は祭衣を着たフレリアの神官、モルダだ。 「戦況は……!? あれからどうなった……っ」 「エフラム様、落ち着きください。エイリーク様、水を」 「はい」 目を醒ますなり尋ねてくるエフラムをなだめ、その背に手を貸してやりながら中年の神官は穏やかな声音でエイリークに水差しを促す。頷いたエイリークがグラスに水を注いで兄に手渡すと、青年は今さらながら声もかすれるほどに自分の喉が渇いていることに気づき、それを一気に飲み干した。 「……ふう」 「落ち着かれましたかな? では、癒しを施させていただきます」 「すまん、頼む」 いくら王子で指揮官であるとはいえ、エフラムなどモルダからすればまだまだ子供のようなものなのだろう。手馴れた様子で彼の裸の肩に手を当てる神官に、エフラムは素直に礼を言ってから視線を妹へと戻した。 「それで、エイリーク。戦況は?」 だが。 「……兄上はそればかりですね」 「何?」 心配そうな顔から一転。可憐な妹にジロリと睨まれて、エフラムは目を白黒させた。 「私たちがどれほど心配したと思っているんですか。あのような無茶をされて……命があ っただけ幸いです」 「う……」 仲間に組になって動けと指示を出しておきながら、その自分が単騎で敵将に挑んでいるようでは世話が無い。最後にデュッセルが間に入らなければ命を失っていたに違いない以上、さすがのエフラムも反論することは出来なかった。 「以後、このようなことは無いようにお願いします」 「わ、わかった。わかったから……泣くな」 まるで子供のように目に涙を溜めて言う妹に、エフラムはこれ以上無くばつの悪い顔でそう言った。エイリークの気丈さを良く知る身としては、どれだけ心配をかけたかも容易に想像出来て、申し訳ない気持ちになる。 もし自分が、エイリークと敵将が一騎打ちする場を遠くから見守るだけの立場であったなら、どのような気分だろうか。 そして、その結果彼女が敵の刃の前に倒れたら? (たまらんな……正直) そんな兄妹に、癒しの祈りをひと段落させてモルダが穏やかに言う。 「他者を救うために己を危険にさらすエフラム様の考えはご立派ですが、ご自分を心配する者がいることもお忘れにならないように。何よりも、あなた様はルネスの王なのですから、もしものことがあってはいけません」 「……わかった。次からはもっと上手くやる」 「もうしないでくださいっ」 「わ、わかった。自重する」 ぐいっと鼻の頭が触れるほどに顔を近づけられ、エフラムは気圧されて約束した。彼も、血を分けた妹にだけは弱い。 それを微笑ましげに眺め、モルダは椅子にかけてあったエフラムの上着を彼に差し出す。袖を通すのを手伝うというエイリークをエフラムが断っているところに、改めてモルダは言った。 「エフラム様。右肩の調子はいかがですか?」 「ああ。多少痛みが残っているが、槍を扱うには支障ない。見事な癒しだ」 傷を受けた時には筋まで断たれたと確信したが、今むき出しの肩には傷一つ無い。傷を受けたことを証明するのは、槍に抉られた部分だけが治癒の魔法によって再生された、真新しい日焼けしていない肌になっていることのみだ。 「並の癒し手ではこうはいかないだろう。さすがだな、モルダ。感謝する」 「残念ながら、その癒しを施したのは私ではありません」 では誰だ、とエフラムが尋ねる前に、エイリークがクスリといたずらっぽく微笑む。 「ラーチェルが必死に癒してくれたんですよ、兄上」 「ラーチェルが?」 確認するようにモルダを見ると、彼も頷いて肯定した。 「快癒の祈りを一刻に渡って続けられていましたな。自らも前線で戦ってきた後だというのに、見事な祈りでした。ロストン正教皇は、素晴らしい後継者をお持ちでいらっしゃる」 「……一刻だと? 無茶をする」 快癒(リカバー)と言えば、並の負傷者に使用すれば一度で全ての傷を癒すことが出来る、高位の神官でなければ使いこなすことの出来ない魔法だ。それを幾度も繰り返されたということは、エフラムがかなり危険な状態だったということだが、それ以上に術者の疲労も恐ろしいほどのはずだ。 「彼女は?」 「さすがに疲れたようで、自分の天幕で休んでいます。あんなにやつれたラーチェルを初めて見ました。大丈夫かしら……」 後半は、報告というよりも、友人を心配する独り言だ。それを受けて、エフラムも神妙に自分の右拳を握り締める。 「油断大敵、か。俺も二度目だな」 「なんですか?」 「いや、こちらの話だ」 それより、とエフラムは視線を天幕の入り口、垂れ幕の方向へと向けた。先程から、その向こうに複数の人物の気配を感じていたのだ。 「用があるなら入れ、ターナ、ミルラ」 「わわ!?」 「…………!?」 呼びかけると、まさか気づかれているとは思っていなかったというふうに、少女二人が驚いた気配が伝わってくる。 それでも彼女たちはしばらくいないふりをしていたが、やがて諦めて垂れ幕の透き間から顔だけを覗かせた。 「エフラム、元気? 入ってもいい?」 「構わないが、どうした? 君らしくもない」 いつもなら、遠慮もなしに幼馴染であるエフラムの部屋に入ってくるターナである。人見知りが激しく、遠慮の強いミルラが入ってこないならば納得出来るのであるが、というエフラムに、ターナはぷうっと頬を膨らませて憤慨する。 「それがね、聞いてよ。お兄さまがね、わたしがエフラムをお見舞いしようとしたら、一国の姫が軽々しく男の部屋に行くなって言うのよ!? しかも、もっと慎み深くしろだなんて、失礼だわ!」 「……ヒーニアスが正しいんだがな」 結局ぷりぷり怒りながらも天幕に入ってくる少女に、エフラムは苦笑した。同じ兄としてヒーニアスの懸念も何となく理解出来るからだ。 カンテラの灯りに照らされたターナは、エフラムから見ても充分に美しく育った女性である。その彼女の欠点と言えば、子供の頃と変わらない甘えたがりな言動と、一度こうと決めたら周りの制止を振り切って国さえも飛び出す無鉄砲さだ。 気さくさのせいか下級の兵士たちにも評判が良く、博打などの遊びにも度々参加しているのを見つけて、兄であるヒーニアスが頭痛を堪えている姿をエフラムは何度も目撃している。 (エイリークと同い年とは思えないな) つまり、自分とも同い年ということなのだが。 変わって、エフラムはターナと共に入ってきた小さな影にも頷いて見せた。それだけでホッとしたように表情を和らげるのは、大陸に二人しか残っていない竜人の片割れ、ミルラだ。 エフラムたちが向かおうとしている闇の樹海で暮らしていたミルラは、極端に人間との触れあいの経験に乏しい。そのせいか、極度の人見知りで、危ういところを助けたエフラム以外の者とはあまり打ち解けていない、寡黙な少女だ。 見た目人間の十歳にも満たない少女は、エフラムの怪我が心配で堪らなかったのだろう。入室の許可が出るなり彼のもとに駆け寄り、その腕を取って顔をすり寄せる。 「心配をかけたな」 「無事なら……いいです」 本物の妹をあやす時と変わらず、エフラムはミルラに接している。それを見てターナなどは、 「いいな~」 と羨ましげにエフラムのもう片方の腕を見るのであるが、 「さ、さすがにそれだけは駄目よ」 エイリークに大人の理性を指摘されて断念した。余人がいなければ、躊躇無く寝台のエフラムに抱きついていたことだろう。 続いて、天幕にはエフラムの側近であるカイルとフォルデが顔を見せた。 カイルは澄ました顔で、 「定時巡回のついでに様子を見に参りました」 と言ったのだが、フォルデの、 「この天幕の前を往復するのが巡回って言うならな」 のひとことで、顔を真っ赤にして彼の首に腕を回して飛び出していった。 呆気に取られるエフラムに、ミルラはボソリと報告する。 「ずっと……いました」 「エフラム、人気者ね。わたし鼻が高いわ!」 何故かターナが自慢げにしているのに首を傾げつつ、エフラムはコホンと咳払いをしてエイリークに言う。 「そろそろ、戦況を聞いてもいいか?」 「はい」 そこからエイリークが語った内容は、だいたいエフラムの想像通りのものだった。エフラムの負傷を皮切りに、連合軍は撤退を開始。ゼトの指揮でこの野営地まで逃げ込んだという。 「グラド帝国軍……まだそう言っていいのかわかりませんが、死者の軍の追撃はありませんでした」 「あくまで時間稼ぎが目的、か。満月は明後日だったな」 頷いたのは、ミルラだった。 竜人の少女は、寒気に自分の小さな肩を抱いて呟く。 「邪悪な力が……どんどん強くなっています……。次の満月の夜、必ず大陸を滅ぼしかねない……何かが起こります……」 「起こさせないさ。そのために、俺たちはここにいるんだからな」 よし、と決断して、エフラムは寝台から床に足を下ろした。ミルラが驚き、助けを求めるようにエイリークを見たが、兄の気性を知る妹はため息をついて首を横に振るだけだった。 「時間が惜しい、軍議を始める。エイリーク、ゼトとデュッセルを呼んでくれ。ターナはヒーニアスを。ミスラはサレフを連れて、今回はお前も軍議に参加してくれ。相手が魔物なら、お前ほど頼りになるものも無い」 「わかりました」 「わかった」 「……はいっ」 少女たちは三者異音同義に頷き、一斉に天幕を走り去って行った。そうしてようやく静かになった場所で、エフラムは黙っていてくれたモルダに苦笑いを見せる。 「賑やか過ぎるのも、考え物だな」 「皆、エフラム様のお役に立てるのが嬉しいのですよ。若いということは良いものです」 「ああ。働くのは若い者でないとな。いつまでもお前やデュッセルに苦労はかけられん」 「……そういう意味では無いのですが」 やはりこの王子もまだまだ『若い』のだと、モルダはひょいと肩をすくめるのだった。 ※ 「まずわかっていることから伝えておこう。あの敵将……グラドでもあれほどの槍の使い手は、わしの知る限り一人しかいない」 夜中に緊急に開かれた軍議の場で、かつてのグラド帝国筆頭将軍は居並ぶ各国の代表者たちを見回した。 「指揮官としての才に恵まれなかったために、将軍職に就くことはなかったが、間違いなくその武人としての才は帝国随一。陛下より柘榴石の二つ名を賜った騎士団長ベルクートに相違あるまい」 「ベルクート……聞かない名前だな」 ルネスの将軍として各国の内部事情にも通じるゼトが、不思議そうにデュッセルに解答を求める。エフラムやヒーニアスも同様で、顔を見合わせて困惑するばかりだ。 しかし、逆に深刻な顔で頷きあう者たちもいる。そうした者は、主に四十代を越える古株たちで、若者たちが生まれる前から己の国のために働いてきた者たちだ。 「ふむ……まさか、あの『グラドの槍』とはのう。これは少々きついかもしれんな」 いつも陽気を崩さないドズラでさえ、己の髭を弄びながら唇を舐める。彼は、エフラムへの施術で疲労しきったラーチェルの名代としての参加だ。 ルネス最古参の戦士であるガルシアも、同意するかのように頷いた。 「ふむ、わしも水城レンバールでの合同訓練で見かけたことがあるが、あれほど見事な槍は後にも先にも見たことが無い。エフラム様。当時、わしらが奴のことを何と言っていたか、教えましょうか」 「なんだ?」 何故そこで自分に話が振られるのか、疑問を顔に浮かべる青年に、ガルシアは試すかのように告げた。 「大陸一の豪槍」 「…………っ」 その言葉は。 その称号は。 まさに、何よりも鋭い槍となってエフラムの心に突き刺さった。 反射的に槍の師であるデュッセルを振り返ったエフラムに、老将は静かに頷いた。青年の気性を理解した上で、ゆっくりと肯定の意を示す。 「そうだ、エフラム。そなたが打ち合った相手こそ、そなたが目指した大陸一の槍使いなのだ。よもや、ここでもう一度あの腕の冴えに出会おうとは、夢にも思わなんだが」 しみじみと、デュッセルはかつての同僚の姿に思いを馳せる。しかし、エフラムはすでにその言葉を聞いてはいなかった。 「あれ……が」 斬り裂かれた右肩を手で押さえ、エフラムは呟く。 (あれが……俺の目指したものか。信じながらも、見果てぬ夢に終わるかと思っていたものか) 最強とは、なんだろう。誰かが最強と言えば、そうなのだろうか。それとも、自分が最強であると確信すれば、それで良いものなのだろうか。 ただ、必要なものだけはわかるのだ。 (事実) 最強であるという、事実。 誰もが最強と認める者を打ち倒した事実。 己が最強と認めた他者を打ち倒した事実。 その者が本当に最強であるとわかるわけではないが、とにかくそれで最強は手に入る。強さとは、常に相対的であり、称号とは常に流動的なものであるからだ。 そして、それは。 柘榴石の騎士は。 「最強で、あり続けているのか。死してなお」 「然り。だからこそ、柘榴石。グラドの紅を冠する槍なのだ」 現在大陸最高の武将であり、屈指の槍使いと認められているデュッセルが無条件に兜を脱いで称賛する。 「リオン皇子は、ベルクートの墓を暴き、死霊魔法で蘇らせたのでしょう。今のリオン皇子であれば、ベルクートを生前そのままの力で動かすことも容易いはずです」 リオンと共に闇魔法を研究していたノールがそう補足し、敵将に関する確認は終わった。 そこから問題になるのは、その攻略法だ。 ゼトが、天馬騎士が上空から写し取った近隣の地図を卓上に広げて一同を見渡した。 「このように、敵軍は闇の樹海の一角を防衛する形の布陣を敷いている。ミルラの話によれば、リオン皇子の向かった魔殿への道筋はそこからの一本のみ。迂回することは出来ず、また相手はただ一晩あそこを死守すれば良いだけ」 それだけで、リオンには充分なのだ。彼は、満月までの時間が稼げればそれで良いのだから。 「なので、少々危険だが総力戦による短期決戦を狙う。サレフ殿の話では、死者たちにはロストン聖騎士団の得意とする光魔法が有効ということだ。彼らを中心に陣を組み、魔力の中心であるベルクートのいる部隊を一気に落とす。もともと我々の方が総数では勝っているので、ベルクートへぶつける魔法使いの数さえ揃えられれば、犠牲も最小限に抑えられるはずだ」 「つまり、自分は死んででも魔法使いを大将前まで連れていけってことか」 そりゃきついなあ、とフォルデが苦笑いを浮かべる。エフラムもそうであったが、誰かを馬の後ろに乗せれば、それは大幅な機動力の低下に繋がる。機動力こそが売りのフォルデたち騎馬兵にとっては、戦力の半分を削がれるようなものだ。 そんな部下のぼやきに、ゼトは神妙に言う。 「だが、逆に言えば万全の騎馬兵をいくらぶつけてもベルクートを討つことは出来ない。それこそ、いたずらに犠牲を増やすだけだ」 「実際、ロストン聖騎士団の脱出を阻んでいたのも、ベルクート一騎だ。ここは、我が軍の魔法使いたちに任せるしかあるまい」 カイルもゼトに同意し、彼らは最後にエフラムを見た。作戦は立案するが、最終的な決定はエフラムに任せるのが彼らのやり方だ。 エフラムは瞼を下ろして思案するが、確かに時間と戦力を考慮するとそれが最善のように思えた。騎士たちに守られた魔法使い数人にかかれば、いかに屈強の戦士であろうと無力だ。あのベルクートでも、安全に滅ぼすことが出来るだろう。 (しかし……) 心に、引っかかるものがある。 自分の中で目を醒まし、声高に主張する『それ』。指揮官として、戦場には絶対に持ち込んではいけないものが、自然と彼の拳を硬く握りこませていた。 だが。 「……そうだな。ゼトの作戦を取ろう。武人としてベルクートに興味はあるが、今はそういうことを言っている時じゃない」 彼は己の喉から出かかった言葉の全てを飲み込んで、そう言った。 ──それが、彼の責任であった。 |
|
| BACK< | >NEXT |